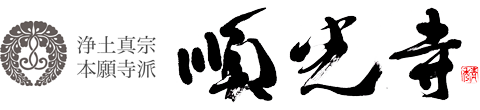お問い合わせの多いご質問と、それに対する回答を掲載しています。
その他不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
順光寺へのご参拝について
駐車スペースがございますので、ご利用ください(バス通り側の参道に3台程度、本堂裏手に10台程度)
なお、順光寺近隣は城下町の町並みが残り、道が狭く見通しも悪いため、気をつけて運転ください(特に裏手の駐車場は川沿にあり、そこに至る交差点も曲がりにくいため、充分ご注意ください)
詳しい経路については、こちらのページをご覧ください。
順光寺の境内は、バス通りからやや奥まった場所にあるため、特にお車で向かわれるとわかりにくいかと思います。
詳しい経路については、こちらのページをご覧ください。
もし迷われたら、順光寺にお電話ください。今おられる場所からの経路を案内いたします。
順光寺電話番号 0852-23-3718
仏事(ご法事・お盆など)について
どちらでもお勤めさせていただきます。事前にご相談ください。
10台程度の駐車スペースを用意いたしております。 詳細については、建物・境内のご案内をご覧ください。
お念珠(ねんじゅ)をお持ちください。お持ちであれば、門徒式章もご用意ください。
浄土真宗本願寺派のお焼香作法は次の通りです。
- 焼香卓の手前で立ち止まって揖拝(一礼)し、左足から卓の前に進みます。
- 右手で香盒(香を入れる器)のふたをとり、香盒の右側の縁に掛け、右手で香を一回だけつまみ、いただかずにそのまま香炉に入れます。
- 香盒のふたを元通りに閉じ、合掌して「南無阿弥陀仏」とお念仏をとなえてから礼拝し、右足から後退し立ち止まって揖拝(一礼)し、退きます。
本堂に椅子がございますのでお使いください。
小さなお子さまがおられる場合、本堂隣にある仏間(和室・八畳二間)をキッズスペースとしてご利用いただけます。お部屋の様子は、建物・境内のご案内をご覧ください。
本堂横に仏間(8畳二間の和室)があり、ご法事の後のご会食にお使いいただけます。
お食事を手配されるときは、配達先を順光寺にご指定ください。
お部屋の様子は、建物・境内のご案内をご覧ください。
ご法事は、故人を偲びながら、今を生きる私達が、阿弥陀如来さまの願いを聞かせていただくものです。ご参拝される皆さまのご都合で調整いただいて結構です。まずは順光寺にご連絡ください。
四十九日のご法事をお勤めした後、最初のお盆のお参りを「初盆」としてお参りさせていただきます。亡くなられた方を偲ぶご縁です。できるだけご親族の皆さまでお勤めください。
SNSを主要連絡ツールにしている方が増えていることもあり、LINEやFacebookメッセンジャーでのご連絡にも対応しております。下記リンクをクリック(タップ)し、ご連絡ください。
※どちらも住職(豅 純吾)の個人アカウントです。
ご葬儀について
身近な方が亡くなられたら、まずはお寺にご連絡ください。臨終勤行(枕経)の日程を決めさせていただき
ます。併せて、葬儀会社にもご連絡ください。
一般的なご葬儀の流れは次の通りです。ご参考ください。
- ご遺体をご自宅や会館に安置された後、臨終勤行(枕経)をつとめます。その時に、お通夜・ご葬儀などの日程を相談させていただきます。葬儀会社の方が同席されると、その後の流れがスムーズになります。
- お葬式の前日に、お通夜のお勤めを行います。
- お葬式をお勤めします。
- 出棺勤行の後、斎場で火屋勤行(ひやごんぎょう)をお勤めします。
※3と4の順番が逆になることもあります。 - 後日、ご自宅のお仏壇で初逮夜(はつたんや)のお勤めを行います。亡くなられた日を1日目とし、6日目の夕方にお勤めします。この時に、四十九日の法要やご納骨の日程を相談させていただきます。
浄土真宗では、「戒名」ではなく「法名」と言います。
法名は、仏法に帰依した人の名前であり、「釋○○」と漢字3文字です。最初に「釋」の字を使うのは、お釈迦さまの弟子であるということです。
本来、法名は、京都・西本願寺で執り行われる「帰敬式(ききょうしき)」を受式し、ご門主からいただくものです。ただし、帰敬式を受けずに亡くなられた場合は、所属寺院の住職が授与します。
お寺の本堂でもご葬儀をお勤めできますので、ご相談ください。
わからないことやお悩みごとがあれば、何なりとお寺にご相談ください。できる限りのお力添えをさせていただきます。
お仏壇について
お仏壇は、ご本尊(阿弥陀如来さま)を安置するところです。また、ご本尊の右側には親鸞聖人(または九字名号)、左側には蓮如上人(または十字名号)のお脇掛を安置します。ご本尊・お脇掛は、本山・西本願寺からお迎えします。事前に順光寺にご連絡ください。
お仏壇にご本尊をお迎えしたら、「入仏式(にゅうぶつしき)」という法要をお勤めします。ご日程などは順光寺にご相談ください。
経机の上にはお経本を置き、右側にはりん(鐘)を台座に乗せて置きます。
なお、ご位牌は浄土真宗では用いません。故人の法名・俗名などは、過去帳に記録します。
お仏壇にはいろいろな形のものがあります。仏具の置き方など、疑問に思われたら、順光寺までお気軽にご相談ください。
お仏壇は、ご家族が一緒に手を合わせ、亡き方を偲びながら仏さまのお慈悲を味あわせていただく場所です。大切にお給仕いたしましょう。
朝、お仏飯をご本尊・お脇掛の前にお供えします。お花は生花をお供えします。枯れたままにならないよう、こまめに変えましょう。
金箔のところは、羽ぼうき(毛ばたき)でそっと埃を払います。手で触れたり布で拭いたりすると、金箔が剥がれることがありますので、ご注意ください。
漆塗りの部分は同様に埃を払い、仏壇用のクロスなどで汚れを拭き取ります
お墓について
浄土真宗のお墓には、形や大きさに決まりはありません。
一番多いのは縦長の墓石を使ったものです。「南無阿弥陀仏」の名号を縦に刻みやすいからです。とはいえ、「こうでなければならない」ということではありません。
皆さんがお参りしやすい方に向けて建ててください。お墓の向きに吉凶はありません。
造花ではなく、生花をお供えください。お花を替えるのが難しい場合はしぶき等の緑だけでも良いです。できる範囲で生花をお供えしましょう。
「あさがら」は、ホームセンターやスーパーのお盆用品コーナーで見かけますが、浄土真宗では用いません。
塔婆に戒名を書いてお墓の前後に建てる宗派もありますが、浄土真宗では用いません。
お墓が完成したら、「建碑式(けんぴしき)」という法要をお勤めします。ご日程などは順光寺にご相談ください。
お墓のことでお悩みでしたら、ご相談ください。できる限りのお力添えをさせていただきます。